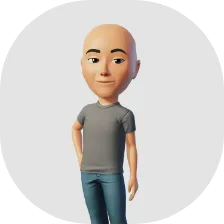伝統文化に触れよう!日本各地の四季のお祭りをご紹介

2023.7.26
地域の人々によって大切に受け継がれ、それぞれの土地の風習が刻み込まれた日本の伝統行事「お祭り」。起源は、紀元前までさかのぼるといわれ、歴史書の古事記(712年)にも「天の岩戸隠れ」という神話として記されています。そんな長い歴史をもつ日本のお祭りの魅力を、季節ごとに詳しくご紹介します!
この記事の目次
- 春 春の到来を告げる例大祭!
- 夏 お祭りハイシーズン!
- 秋 収穫を祝い豊作を祈願する大祭!
- 冬 生命力を蘇らせる冬のお祭り!
- 日本三大花火も!幻想的な花火が楽しめる花火大会3選
- 一度は行ってみたい!インパクト絶大のお祭り2選
- ロマンチックな夜を楽しもう!日本のランタンイベント2選
- まとめ
春 春の到来を告げる例大祭!
寒く長い冬を経て、木々がゆったりと芽吹き始める春。各地で春の到来を喜ぶかのようにさまざまなお祭りが行われます。伝統を感じさせる神社の例大祭が各地で行われるほか、自然の美しさを堪能できる桜まつりも多くの観光客を魅了します。お祭りを通してその土地の新たな一面と出会うことができるでしょう。
春の高山祭(岐阜)

岐阜県高山市に春の訪れを告げる日枝神社の例大祭、通称「山王祭」。豪華絢爛な12台の祭屋台に加え、闘鶏楽(とうけいらく)や裃姿(かみしもすがた)の警固など伝統衣装の祭行列が行き交うその光景は、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのよう。14日夜に開催される夜祭では提灯で祭屋台がライトアップされ、幻想的な雰囲気を醸し出します。なお、毎年10月には秋の高山祭(八幡祭)も開催。こちらは櫻山八幡宮の例祭※となるもので、高山祭とは通常、春と秋のふたつのお祭りを指す総称とされています。
※神社で行われる年1回の代表的大祭
- 開催時期
- 毎年4/14~4/15
- 会場
- 岐阜県高山市神明町ほか
- 電話番号
- 0577-35-3145
高山市役所観光課
最寄り空港からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
- 最寄り空港からの移動時間
- 車の場合:約4時間30分
公共交通機関の場合:約5時間10分
- アクセス方法
- 大阪国際空港(伊丹空港)から、リムジンバスで新大阪駅へ。東海道・山陽新幹線に乗り換えて名古屋駅へ。東海道本線に乗り換えて岐阜駅へ。ひだに乗り換え高山駅へ、徒歩約18分。
弘前さくらまつり(青森)

弘前市中心部に広がる弘前公園は、総面積約49万2千平方メートルを誇る市民の憩いの場。その中心には東北で唯一現存する天守である弘前城がどっしりと構えており、その弘前城を囲むように52種類・約2,600本の桜が植えられています。桜の開花と共に開催される弘前さくらまつりは、弘前公園が1年でもっとも美しい瞬間ともいえるでしょう。ソメイヨシノやシダレザクラ、八重桜など、色とりどりの桜が咲き誇る光景は圧巻。夜になれば弘前城がライトアップされ、桜との美しいコントラストを描きます。
桜の名所22選の記事はこちら
- 開催時期
- 4月中旬~5月上旬
- 会場
- 弘前公園 青森県弘前市下白銀町1
- 電話番号
- 0172-35-3131
弘前観光コンベンション協会
- URL
- http://www.hirosakipark.or.jp/hirosakipark/index.html
弘前公園に関するサイト:弘前市みどりの協会
関西からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
神戸空港
- 到着空港
- 青森空港
- 飛行時間
- 約1時間40分
- 到着空港からの移動時間
- 車の場合:約40分
公共交通機関の場合:約1時間30分
- アクセス方法
- 青森空港からリムジンバスで弘前駅前下車、徒歩約25分。
- 予算(片道)
- 約2万4千円~
夏 お祭りハイシーズン!
夏は日本各地でバラエティに富んだお祭りが開催されます。伝統的なお祭りから踊り手たちのエネルギー溢れる盆踊り、煌びやかな花火大会、近年創作された新しいお祭りまで、夏はお祭りのハイシーズンともいえるでしょう。普段の観光旅行とはひと味違うディープな体験をできるのもお祭りの魅力です。
秋田竿燈まつり(秋田)

青森のねぶた祭り、仙台の七夕まつりと並ぶ東北三大祭りのひとつ。約280本もの竿燈(かんとう)が会場となる竿燈大通りを明るく照らし出す、秋田の夏の風物詩です。46個の提灯を下げた高さ約12mの竿燈の重さは約50kg。竿燈を担ぐ差し手たちが「ドッコイショー、ドッコイショー」の掛け声と共に重い竿燈を巧みに操ると、沿道の観客から大きな声が上がります。真夏の病魔や邪気を払うねぶり流し行事が原点とされ、数百年の歴史を誇る由緒正しいお祭りです。
この7月には大阪国際空港(伊丹空港)でもその雰囲気を味わえる「秋田竿燈サマーフェスタ 」が開催されました。
竿燈演技の様子
差し手の息を吞むようなパフォーマンスで、会場内は熱気に包まれ、秋田グルメの飲食物販ブースやクイズイベント、お子さま向けのミニ竿燈チャレンジなどを実施しました。


- 開催時期
- 毎年8/3~8/6
- 会場
- 秋田県秋田市竿燈大通り
- 電話番号
- 018-888-5602
秋田市竿燈まつり実行委員会事務局(秋田市観光振興課内)
関西からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
- 到着空港
- 秋田空港
- 飛行時間
- 約1時間30分
- 到着空港からの移動時間
- 車の場合:約30分
公共交通機関の場合:約50分
- アクセス方法
- 秋田空港からリムジンバスで秋田駅へ。
徒歩約5分で竿燈大通りへ到着。
- 予算(片道)
- 約2万2千円~
天神祭(大阪)

日本各地の天満宮(天神社)で開催される天神祭のなかでも最大規模を誇るのが大阪の天神祭です。京都の祇園祭、東京の神田祭と共に日本三大祭りのひとつに数えられ、その歴史は1,000年以上。6月下旬からの約1か月間、鉾流神事(ほこながししんじ)や水上薪能(すいじょうたきぎのう)などさまざまな行事が行われます。メインとなるのは7月25日の本宮の夜。大川(旧淀川)に多くの船が行き交う船渡御(ふなとぎょ)が行われ、色鮮やかな奉納花火が夏の夜を彩ります。火と水の祭典とも呼ばれており、ドラマチックな一夜を体験できることでしょう。
- 開催時期
- 毎年6月下旬~7/25
- 会場
- 大阪府大阪市北区天神橋2-1-8 大阪天満宮など
- 電話番号
- 06-6353-0025
大阪天満宮
最寄り空港からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
- 最寄り空港からの移動時間
- 公共交通機関の場合:約60分
- アクセス方法
- 大阪国際空港(伊丹空港)からモノレールで山田駅へ。阪急千里線に乗り換え、直通堺筋線南森町駅下車。徒歩約4分。
秋 収穫を祝い豊作を祈願する大祭!
稲などの農作物の収穫期にあたる秋は、日本人にとって実りの季節であり、そのことを神々に感謝するさまざまなお祭りや伝統行事が行われてきました。そこに込められているのは、収穫を祝い、翌年の豊作を祈願する切実な思いです。各地域における一大イベントであると同時に、その土地の魂を刻み込んだお祭りに触れてみましょう。
大津祭(滋賀)

琵琶湖の南西岸に位置し、古くから湖上交通の要所となってきた滋賀県大津市。同地を代表するお祭りが、天孫神社の祭礼である大津祭です。艶やかな曳山(ひきやま)※のもとで祭り囃子(まつりばやし)が演奏される本祭前夜の宵宮(よいみや)に続き、本祭では13基の曳山が登場。市内を勇ましく練り歩きます。各曳山には精巧に作られたからくり人形が乗り、観るものの目を楽しませてくれます。なお、からくりを演じることを所望(しょうもん)と言い、本祭の巡行中、20数か所でこの所望が行われます。
※飾り物を据えた山車(だし)
- 開催時期
- 毎年10月第2月曜日前の土曜日・日曜日
- 会場
- 滋賀県大津市京町3‐3‐36 天孫神社など
- 電話番号
- 077-522-3593
天孫神社
最寄り空港からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
- 最寄り空港からの移動時間
- 公共交通機関の場合:約1時間30分
- アクセス方法
- 大阪国際空港(伊丹空港)からモノレールで蛍池駅へ。宝塚本線に乗り換え大阪梅田駅へ。徒歩で大阪駅へ移動し東海道・山陽本線で大津駅へ。徒歩約4分。
唐津くんち(佐賀)

唐津神社(佐賀県唐津市)の秋季例大祭が唐津くんちです。くんちとは「供日(くにち)」が九州の方言で訛ったものとも言われています。
初日となる宵山(毎年11/2)では14台の曳山が唐津の城下町を廻り、翌3日は唐津くんち最大の祭事であるお旅所祭が斎行されます。獅子や鯉、兜などをかたどった曳山はインパクト十分。荘厳でありながらどこかチャーミングな造形に魅了されます。最終日となる4日は曳山が町中を巡行する町廻りが行われます。
- 開催時期
- 毎年11/2~11/4
- 会場
- 佐賀県唐津市南城内3-13 唐津神社など
- 電話番号
- 0955-74-3355
唐津観光協会
関西からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
関西国際空港
- 到着空港
- 福岡空港
- 飛行時間
- 約1時間20分
- 到着空港からの移動時間
- 車の場合:約60分
公共交通機関の場合:約2時間
- アクセス方法
- 福岡空港からリムジンバスで博多駅へ。七隈線に乗り換えて天神南駅へ。西鉄天神高速バスターミナルでからつ号に乗り大手口バス停下車、徒歩約5分。
- 予算(片道)
- 約1万円~
冬 生命力を蘇らせる冬のお祭り!
1年でもっとも寒く、太陽の力が弱まる冬、ひとびとは生命力を蘇らせるためのお祭りや神事を必要としてきました。そこには厳しい冬を乗り越え、生きながらえるための願いが込められていました。そうした冬祭りを象徴するふたつのお祭りをご紹介します。
なまはげ柴灯まつり(秋田)

秋田県の男鹿(おが)半島では各集落ごとになまはげが受け継がれてきました。大晦日の夜に「泣く子はいねがー」と叫びながら家々を回るその風習は、年の節目にやってくる来訪神の文化を受け継ぐものでもあります。なまはげ柴灯(さいとう)まつりは、このなまはげと真山神社の神事である柴灯祭を組み合わせるかたちで昭和39年に始まった冬の観光行事。大晦日のなまはげ行事が再現されるほか、柴灯火を背に踊る「なまはげ踊り」や郷土芸能である「なまはげ太鼓」も演じられます。
秋田の観光記事はこちら
- 開催時期
- 毎年2月第2金曜日〜日曜日
- 会場
- 秋田県男鹿市北浦真山水喰沢97 真山神社
- 電話番号
- 0185-24-9210
なまはげ柴灯まつり実行委員会(男鹿市観光課内)
関西からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
- 到着空港
- 秋田空港
- 飛行時間
- 約1時間30分
- 到着空港からの移動時間
- 車の場合:約1時間10分
公共交通機関の場合:約1時間40分
- アクセス方法
- 秋田空港から男鹿半島号(要前日予約)でなまはげ館下車、徒歩約4分。
- 予算(片道)
- 約2万2千円~
新野の雪祭り(長野)


愛知県にもほど近い長野県の県境の地、阿南町新野で続く豊作祈願のお祭りです。幸法(さいほう)様や茂登喜(もどき)、お牛様、松影、神婆など個性豊かな神々が登場し、夜を徹して多種多様な芸能を披露。雪を稲穂の花に見立て、雪が降るほど豊作になるとされています。大正15年には民俗学者の折口信夫がこの祭りを見学し、その衝撃を綴ったことから多くのお祭り愛好家にその名が知られるようになりました。それまでは正月神事や田楽祭りと呼ばれていましたが、以降、新野の雪祭りという名が定着しました。
- 開催時期
- 毎年1/13~1/15
- 会場
- 長野県下伊那郡阿南町新野2608 伊豆神社
- 電話番号
- 0260-22-4055
阿南町役場 振興課農業商工係鹿市観光課内
最寄り空港からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
- 最寄り空港からの移動時間
- 車の場合:約4時間30分
公共交通機関の場合:約7時間10分
- アクセス方法
- 大阪国際空港(伊丹空港)から、リムジンバスで新大阪駅へ。東海道・山陽新幹線に乗り換えて名古屋駅へ。名鉄バスセンターから飯田駅前バス停下車、南部公共バスに乗り換え寺山バス停下車、徒歩約4分。
日本三大花火も!幻想的な花火が楽しめる花火大会3選
「日本のお祭り」と聞き、夜空に花火が打ち上げられる光景を連想される方は多いことでしょう。現在では夏のビッグイベントとして各地でさまざまな花火大会が行われていますが、かつては精霊や死者の供養のために花火が打ち上げられることもありました。そんな花火大会の一例をご紹介します。
土浦全国花火競技大会(茨城)

長岡まつり大花火大会(新潟県長岡市)や、全国花火競技大会大曲(おおまがり)の花火(秋田県大仙市)と並ぶ日本三大花火大会のひとつといわれています。大正14年、神龍寺(じんりゅうじ)(土浦市文京町)の住職だった秋元梅峯(あきもとばいほう)氏が、航空隊殉職者の慰霊と関東大震災後の不況で疲弊した土浦の経済を活性化するべく、私財を投じて開催したのが始まりです。土浦の花火大会といえば、やはり速射連発の打ち上げ方法であるスターマイン。現在では「スターマイン日本一」を決める大会とも言われています。多種多様な花火が秋空を彩る様は壮観そのものです。
- 開催時期
- 毎年11月第1土曜日
- 会場
- 茨城県土浦市桜川河川畔(学園大橋付近)
- 電話番号
- 029-826-1111
土浦全国花火競技大会実行委員会事務局
関西からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
関西国際空港
- 到着空港
- 成田国際空港
- 飛行時間
- 約1時間35分
- 到着空港からの移動時間
- 約1時間30分〜2時間
- アクセス方法
- 成田空港からバスか電車でJR土浦駅へ。シャトルバスに乗り換え約10分で到着。
- 予算(片道)
- 約8千円~
洞爺湖ロングラン花火大会(北海道)


近年、夏の一定期間花火が打ち上げられるロングラン花火大会が各地で行われています。限られた期間しかその地を訪れることができない観光客にとっては、確実に花火が見られるとあって人気を集めています。なかでも2023年で42回目を迎える洞爺湖ロングラン花火大会は、洞爺湖の雄大なロケーションをバックに約450発の花火が毎夜打ち上げられることから根強い人気を誇ります。湖を移動する船の上から打ち上げられるため、湖畔のどの場所からも迫力ある花火を楽しめるところもポイント。

- 開催時期
- 毎年4/28~10/31
- 会場
- 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉
- 電話番号
- 0142-75-2446
洞爺湖温泉観光協会
関西からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
関西国際空港
神戸空港
- 到着空港
- 新千歳空港
- 飛行時間
- 約2時間
- 到着空港からの移動時間
- 車の場合:約1時間30分
公共交通機関の場合:約2時間
- アクセス方法
- 新千歳空港から快速エアポートで南千歳駅へ。北斗に乗り換えて洞爺駅へ。道南バスでコミュニティーセンター前下車、徒歩約5分。
- 予算(片道)
- 約1万2千円~
日本ライン夏まつりロングラン花火(愛知)

8月の10日間にわたって開催されるこの花火大会は、東海地区を代表する花火大会のひとつです。舞台となるのは愛知県犬山市と岐阜県各務原市の境を流れる木曽川。期間中は毎晩午後8時からの約10分間、200発から300発の花火が惜しげなく打ち上げられます。色とりどりの花火の背景には天文6年に織田信長の叔父・信康が築城した犬山城。現存する日本最古の天守であり、国宝に指定されている名城とともに花火を楽しめるのは最高の贅沢といえるでしょう。

- 開催時期
- 毎年8/1~8/10
- 会場
- 愛知県犬山市木曽川河畔
- 電話番号
- 0568-61-2825
犬山市観光協会
最寄り空港からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
- 最寄り空港からの移動時間
- 車の場合:約3時間
公共交通機関の場合:約3時間
- アクセス方法
- 大阪国際空港(伊丹空港)から、リムジンバスで新大阪駅へ。東海道・山陽新幹線に乗り換えて名古屋駅へ。名鉄名古屋本線に乗り換えて犬山遊園駅下車、徒歩約1分。
一度は行ってみたい!インパクト絶大のお祭り2選
お祭りとは本来一年に一度の非日常を生み出すものでもあります。そのために特別な装束を着たり、豪華な飾りつけをした装置を必要としたりします。そうした非日常を体験できるお祭りを、関西からアクセスしやすい2箇所に絞ってご紹介します。
岸和田だんじり祭(大阪)

西日本では「だんじり」と呼ばれる山車を曳き回すだんじり祭りが各所で行われています。もっとも知られているのが岸和田のだんじり祭。最大重量4トンを越えるだんじりを数百人で勢いよく引っ張るこのお祭りの最大の特徴は、猛スピードでカーブに突入する「やりまわし」です。また、だんじり囃子の心地よいリズムも魅力のひとつ。だんじりの細かな装飾や祭りの背景も含め、荒々しいだけではない奥深い魅力のあるお祭りです。

- 開催時期
- 毎年9月中旬
- 会場
- 大阪府岸和田市岸和田地区など
- 電話番号
- 072-423-2121(代表)
岸和田市観光課観光振興担当
最寄り空港からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 関西国際空港
- 最寄り空港からの移動時間
- 車の場合:約20分
公共交通機関の場合:約30分
- アクセス方法
- 関西国際空港から南海空港線で岸和田駅へ。徒歩約10分。
西大寺会陽(岡山)

天下の奇祭として広く知られている岡山県岡山市の西大寺会陽、別名「はだか祭り」。数百年の歴史あるお祭りです。まわしを締めた約10,000人の男性たちが奪い合うのは、西大寺観音院の本堂である御福窓から投げ込まれる2本の宝木。手にしたものは福男と呼ばれ、福が約束されるといわれています。参加者は事前に心身を清める必要があるほか、本堂の本尊千手観音と鎮守堂の牛玉所大権現を詣でるなど、歴史あるお祭りだけに厳粛な雰囲気のなかで行われます。
- 開催時期
- 毎年2月第3土曜日
- 会場
- 岡山県岡山市東区西大寺中3-8-8 金陵山西大寺
- 電話番号
- 086-942-0101
西大寺会陽奉賛会
最寄り空港からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 関西国際空港
- 最寄り空港からの移動時間
- 車の場合:約3時間
公共交通機関の場合:約2時間40分
- アクセス方法
- 関西国際空港からはるかで新大阪駅へ。東海道・山陽新幹線に乗り、岡山駅へ。赤穂線に乗り換え、西大寺駅へ。徒歩約13分。
ロマンチックな夜を楽しもう!日本のランタンイベント2選
アジア各地では明かりを灯したランタン(中国提灯)を飾ったり、空へと飛ばす風習がありますが、近年では日本でもランタンを用いたイベントが増えてきました。ロマンチックな夜を楽しめるランタンイベントを2つご紹介します。
長崎ランタンフェスティバル(長崎)

起源となるのは、長崎新地中華街の人々が中国の旧正月(春節)を祝うために行っていた春節祭。それが平成6年から規模を拡大し、長崎市内各地にランタンを飾る長崎ランタンフェスティバルとして開催されるようになりました。その数は約1万5千個。長崎市内はランタンの明かりに包み込まれます。また、清朝時代の皇帝・皇后の行進をイメージしたパレードや媽祖(まそ)行列、雨乞いの神事をもとにした龍踊りなど、多種多様なイベントが行われます。

- 開催時期
- 毎年春節に合わせて2週間開催
- 会場
- 長崎県長崎市湊公園、新地中華街、中央公園など
- 電話番号
- 095-822-8888
長崎市コールセンターあじさいコール
関西からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 大阪国際空港(伊丹空港)
関西国際空港
神戸空港
- 到着空港
- 長崎空港
- 飛行時間
- 約1時間15分
- 到着空港からの移動時間
- 車の場合:約40分
公共交通機関の場合:約40分
- アクセス方法
- 長崎空港からリムジンバスで長崎新地バス停下車、徒歩約3分。
- 予算(片道)
- 約6千円~
南紀白浜ドリームランタン(和歌山)

2022年に初開催された新感覚のランタンイベント。LED電球が入った1,000個ものランタンを夜空に放つというもので、事前に購入すると願いごとを書いた短冊をランタンに貼り付けることができるそう。また、「音と灯りのコラボレーション」というテーマが掲げられていることからもわかるように、音楽に合わせて色を変えるバルーンも幻想的な雰囲気を盛り上げてくれます。まだまだ始まったばかりの新しいイベントではありますが、何十年と続くなかで白浜の伝統となっていくのかもしれません。
- 開催時期
- 9/30 順延日10/1(2023年)
- 会場
- 和歌山県西牟婁郡白浜町864 白良浜
- 電話番号
- 0739-43-3201
(一社)南紀白浜観光協会事務局
最寄り空港からの行き方(アクセス)
- 出発空港
- 関西国際空港
- 最寄り空港からの移動時間
- 車の場合:約1時間30分
公共交通機関の場合:約2時間50分
- アクセス方法
- 関西国際空港から関西空港線で白浜駅へ。バスで白浜田辺線白良浜バス停下車、徒歩すぐ。
まとめ
お祭りにはその土地の風土や歴史が刻まれています。そのため、通常の観光旅行とはひと味違うディープな体験ができるはず。もちろん、各地域ならではの食やアクティビティと合わせて楽しむことも可能です。コロナ禍の規制がようやく緩和されてきた今年こそ、思う存分お祭りを堪能できるのではないでしょうか。
※本記事は2023年6月19日現在の情報です。
New新着記事
Ranking人気記事
関西発の旅がもっと楽しくなる、
空港公式メディア
FLY from KANSAIは、関西3空港(KIX・ITAMI・KOBE)からはじまる旅の魅力や楽しみ方をお届けする空港公式メディアです。
FLY form KANSAIとは